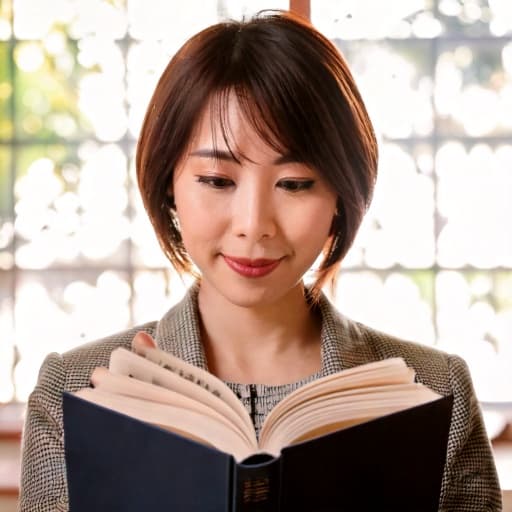はじめに:ECサイト開業に必要な許可・資格とは?
ECサイトを開業し、商品を販売するには、実店舗を持つ場合と同様に、さまざまな許可や資格が必要になる場合があります。フリマアプリで不用品を売るのとは異なり、ビジネスとして継続的に商品を販売するには、法律に基づいた手続きが求められるのです。
特に、取り扱う商品によっては、特定の許可や資格が必須となります。これらは商品の安全性や取引の健全性を保つために国や自治体が定めているものです。
具体的には、以下のような項目について確認が必要です。
-
商品を販売するための許可や資格: 取り扱う商品によって必要
-
商品の表示に関するきまり: 消費者への正しい情報提供のため
-
ECサイトを運営するための法律: 特定商取引法など
-
ECサイト開業時の届出: 税務署への開業届など
これらの許可や資格、関連法規を理解し、適切に対応することが、スムーズで安心なECサイト運営の第一歩となります。
ECサイト開業前に確認すべき法律
ECサイトを始めるにあたっては、遵守すべき様々な法律があります。これらの法律を知らずに運営すると、思わぬトラブルや罰則の対象となる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
特に重要なのが「特定商取引法」です。これは、通信販売などにおいて消費者を保護するための法律で、事業者名、住所、電話番号、販売価格、送料、返品特約などの情報をサイト上に分かりやすく表示することが義務付けられています。
その他にも、販売する商品や広告方法によっては、以下の関連法規も確認が必要です。
-
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法): 虚偽や誇大な広告表示を規制します。
-
不正競争防止法: 競争相手に損害を与えるような不正な競争行為を規制します。
-
食品衛生法: 食品の安全に関するルールを定めています(食品を扱う場合)。
-
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律): 医薬品、化粧品、医療機器などを扱う場合に適用されます。
-
酒税法: 酒類を販売する場合に適用されます。
-
古物営業法: 中古品を扱う場合に適用されます。
取り扱う商品によって適用される法律が異なるため、ご自身のECサイトで何を販売するかを明確にした上で、関係する法律を確認し、必要な手続きを進めるようにしましょう。
特定商取引法
ECサイトを運営する上で、まず理解しておくべき重要な法律が「特定商取引法」です。この法律は、事業者による不公正な勧誘行為等から消費者を守るためのルールを定めています。特に通信販売(ネット販売)に関しては、以下のような情報の表示が義務付けられています。
|
表示項目 |
具体例 |
|---|---|
|
事業者の氏名(名称) |
個人事業主の場合は氏名、法人の場合は登記されている名称 |
|
住所 |
個人事業主の場合は現住所、法人の場合は登記されている本店所在地 |
|
電話番号 |
消費者からの問い合わせに対応できる連絡先 |
|
代表者または責任者 |
法人の場合は代表者、個人事業主の場合は本人または運営責任者の氏名 |
|
販売価格 |
商品・サービスの税込価格 |
|
送料 |
送料の金額や計算方法 |
|
代金の支払方法 |
クレジットカード、銀行振込など利用可能な支払方法 |
|
支払時期 |
代金支払いが発生するタイミング |
|
商品の引渡時期 |
注文から商品が届くまでの期間や発送方法 |
|
返品に関する特約 |
返品の可否、条件、期限、送料負担など(特約がない場合は特定商取引法に基づく返品ルールが適用されます) |
|
申込みの有効期限 |
期間限定販売などの場合 |
|
ソフトウェアなどの動作環境 |
デジタルコンテンツの場合 |
|
問い合わせ先 |
連絡先情報 |
これらの情報を正確かつ分かりやすく表示することは、消費者との信頼関係構築と、法律違反のリスク回避のために不可欠です。特に返品に関するルールは、トラブルになりやすいため、明確に記載する必要があります。
その他の関連法規(景品表示法、不正競争防止法など)
ECサイトを運営する上で、特定商取引法以外にも遵守すべき法律があります。特に重要なのが「景品表示法」と「不正競争防止法」です。
景品表示法は、商品やサービスの品質、価格などを偽って表示する「不当表示」や、過大な景品を提供することを規制し、消費者が安心して商品を選べるように保護する法律です。具体的には、実際よりも優れているかのように見せかける「優良誤認表示」や、実際よりも有利であるかのように見せかける「有利誤認表示」などが禁止されています。
|
不当表示の種類 |
具体例 |
|---|---|
|
優良誤認表示 |
カシミヤ80%なのに「カシミヤ100%」と表示 |
|
有利誤認表示 |
全員当選なのに「先着100人限定」と表示 |
また、2023年10月からは、広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」も規制対象となりました。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律で、他の事業者の信用を傷つけたり、模倣品を販売したりといった不正行為を禁止しています。
これらの法律に違反すると、消費者庁からの措置命令や課徴金納付命令、さらには罰則が科される可能性もあります。ECサイトの信頼性を保つためにも、正しく理解し、遵守することが非常に重要です。
販売品目別に必要な許可・資格
ECサイトで取り扱う商品によっては、法律に基づいた許可や資格が必要になります。これは、実店舗で販売する場合と同様です。必要な許可や資格を取得しないまま販売を行うと、法律違反となり、トラブルや営業停止につながる可能性があります。
主な販売品目と必要な許可・資格は以下の通りです。
|
販売品目 |
必要な許可・資格等 |
関連法規 |
|---|---|---|
|
中古品 |
古物商許可 |
古物営業法 |
|
食品(製造・加工を行う場合) |
食品衛生法に基づく営業許可、食品衛生責任者 |
食品衛生法、自治体条例 |
|
酒類 |
酒類販売業免許(一般、通信販売など) |
酒税法 |
|
医薬品(一般用医薬品) |
薬局開設許可、医薬品販売許可など |
医薬品医療機器等法(薬機法)、薬剤師法 |
|
化粧品(製造を行う場合) |
薬機法に基づく許可 |
薬機法 |
|
健康食品(保健機能食品) |
特定保健用食品は消費者庁長官の許可 |
薬機法、健康増進法など |
|
ペット・動物 |
動物取扱業の届出 |
動物の愛護及び管理に関する法律 |
|
輸入品 |
各種法令に基づく手続き |
関税法、食品衛生法など |
ただし、商品の状態や販売方法によっては許可が不要なケースもあります。例えば、自分で使用したものを販売する場合や、パッケージされた食品を開封せずに販売する場合などです。詳細は各品目の項目で解説します。
中古品(古物商許可)
ECサイトで中古品を販売する場合、原則として「古物商許可」が必要です。これは、盗品の流通を防ぎ、被害回復を目的とする古物営業法に基づくものです。継続的に中古品を販売する場合(副業含む)や、リサイクルショップの運営、ネットオークション・フリマでの反復継続的な販売などが該当します。
古物とは?
一度使用された物品、または未使用でも一度取引された物品、これらをメンテナンスした物品などを指します。具体的には、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品、書籍、金券類など13品目に分類されます。スマホやタブレットなどの最新機器は、警察署への確認をおすすめします。
許可が不要なケース
すべてのケースで許可が必要なわけではありません。以下のような場合は不要となることが多いです。
-
自宅の不用品を売る場合(転売目的で購入したものを除く)
-
無償でもらったものを売る場合
-
自分が売った相手から買い戻す場合
-
海外で購入したものを国内で売る場合
申請方法の概要
管轄の警察署に申請書類一式を提出します。手数料19,000円がかかり、許可が下りるまで通常40日程度かかります。申請には、申請書、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、URLの使用権限疎明資料などが必要です。
取得後の手続き
ネット上で取引を行う場合、「URL届出(変更届出書)」が必要です。
古物商許可が必要なケース、不要なケース
ECサイトで中古品を販売する場合、原則として「古物商許可」が必要です。これは、盗品の流通を防ぎ、速やかに発見することを目的とした「古物営業法」に基づいています。
具体的に許可が必要となるのは、以下のようなケースです。
-
中古品を買い取って販売する(修理して販売、部品取りして販売なども含む)
-
委託を受けて中古品を販売し、手数料を得る
-
中古品と他の物品を交換する
-
中古品を買い取ってレンタルする
-
国内で買い取った中古品を海外で販売する(輸出)
一方で、以下のような場合は許可が不要です。
-
自分が使用していたものを販売する
-
無償で譲り受けたものを販売する
-
相手から手数料を取って回収したものを販売する
-
自分が販売した相手から同じものを買い戻す
-
海外で購入したものを国内で販売する(輸入)
ご自身の販売形態がどちらに当てはまるか、事前にしっかり確認しましょう。
申請方法の概要(必要書類、申請先など)
古物商許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。申請に必要な書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。
-
申請書
-
住民票の写し
-
身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
-
誓約書(欠格事由に該当しないことなどを誓約するもの)
-
略歴書
-
URL使用権限を証明する書類(ご自身のネットショップのURLを使用する場合)
-
手数料(申請時に必要な法定費用)
これらの書類に加え、場合によっては追加書類の提出を求められることがあります。事前に管轄の警察署のWebサイトなどで最新の情報をご確認いただくか、直接問い合わせることをお勧めします。
食品衛生法に基づく許可・届出
ECサイトで食品を販売する場合、食品衛生法に基づいた許可や届出が必要となることがあります。これは、実店舗での販売と同様です。
必要な許可・届出の例
-
営業許可:
-
食品の製造や加工を行う場合(例: 菓子製造、惣菜製造など)
-
製造された食品を小分けにして再包装する場合
-
飲食店や喫茶店など
-
-
食品衛生責任者の設置:
-
営業許可施設ごとに1名配置が義務付けられています。資格取得講習会などで取得できます。
-
許可・届出が不要なケース
-
農作物を生産者から直接配送する場合
-
パッケージされた既製の商品を、開封・加工せずにそのまま販売する場合(例: スナック菓子、缶詰など)
-
調理済みの食品(弁当、惣菜パンなど)を仕入れてそのまま販売する場合
ただし、自治体によっては独自の条例で届出が必要な場合もありますので、詳細は管轄の保健所に確認することをおすすめします。
申請は、営業所を管轄する保健所で行います。
食品表示に関するルール
ECサイトで食品を販売する際には、食品表示法に基づいた正確な情報表示が義務付けられています。これは、消費者が安全に食品を選べるようにするためです。
表示すべき主な項目は以下の通りです。
-
名称
-
原材料名
-
添加物
-
内容量
-
消費期限または賞味期限
-
保存方法
-
製造者または販売者の氏名・名称、住所
特に注意が必要なのは、アレルギー物質の表示です。特定原材料(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生)やそれに準ずるものについては、原則として表示が義務付けられています。
また、健康食品についても表示には注意が必要です。医薬品と誤解されるような効果効能の表示は薬機法で禁止されています。「特定保健用食品(トクホ)」や「機能性表示食品」といった保健機能食品については、消費者庁長官の許可や届け出に基づいた表示ルールがあります。
正確な表示は、消費者からの信頼を得るためにも非常に重要です。
酒類
ECサイトで酒類を販売するには、原則として「酒類販売業免許」が必要です。主に以下の3種類がありますが、ネット販売で全国を対象とする場合は「通信販売酒類小売業免許」を取得します。
-
通信販売酒類小売業免許
-
対象:2都道府県以上(全国)
-
方法:インターネット、カタログなど
-
扱える酒類:国産の場合、年間出荷量3,000kl未満の蔵元製造品に限る。輸入品に制限なし。
-
-
一般酒類小売業免許
-
対象:店舗所在地と同一都道府県内
-
方法:店舗販売、通信販売
-
-
特殊酒類小売業免許
-
特殊な場合(例:社内販売)
-
通信販売酒類小売業免許の取得には、税務署への申請が必要です。申請には多くの書類が必要となり、審査には通常2ヶ月ほどかかります。販売したい酒類(特に国産品)の蔵元から証明書を取得する必要があるため、事前の準備が重要です。
酒類販売業免許
ECサイトで酒類を販売するには、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。これは、2都道府県以上の消費者を対象に、インターネットなどを通じて酒類を販売するための免許です。店頭販売を行う場合は、別に「一般酒類小売業免許」が必要になります。
通信販売酒類小売業免許を取得するには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。
-
人的要件: 申請者が過去に問題を起こしていないか。
-
場所的要件: 販売所が製造所や飲食店と同一でないか。
-
経営基礎要件: 経営状態や販売管理体制が適切か。
-
需給調整要件: 販売できる酒類の種類が限定されているか(国産酒は年間出荷量3,000kl未満の製造者のものなど)。
申請は、事務所を管轄する税務署で行います。申請には多岐にわたる書類が必要となり、審査には2ヶ月程度かかります。
医薬品・高度管理医療機器
医薬品や高度管理医療機器をECサイトで販売する場合、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づいた許可が必要です。
|
医薬品の種類 |
ECサイト販売の可否 |
販売主体・条件 |
|---|---|---|
|
医療用医薬品 |
不可 |
|
|
要指導医薬品 |
不可 |
|
|
一般用医薬品 |
可能 |
薬局開設者が、医薬品販売業許可と特定販売許可を取得 |
|
– 第一類医薬品 |
可能 |
薬剤師による販売が必要 |
|
– 第二類医薬品 |
可能 |
薬剤師または登録販売者の在籍が必要 |
|
– 第三類医薬品 |
可能 |
薬剤師または登録販売者の在籍が必要 |
ECサイトで医薬品を取り扱うには、薬局を開設し、さらに医薬品販売業許可と**特定販売(インターネット販売許可)**を取得する必要があります。
申請は、所轄の保健所や各都道府県の薬事課で行います。不明な点があれば、事前に相談することをおすすめします。
高度管理医療機器の販売には、別途、薬機法に基づく「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可」が必要です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に基づく許可
ECサイトで医薬品や高度管理医療機器などを販売する場合、薬機法に基づいた許可や届出が必要です。薬機法は、これらの製品の品質、有効性、安全性を確保し、保健衛生上の危害を防止することを目的としています。
薬機法の対象となる主な製品は以下の通りです。
-
医薬品(処方箋医薬品、一般用医薬品など)
-
医薬部外品
-
化粧品
-
医療機器(体温計、血圧計、コンタクトレンズなど)
-
体外診断用医薬品
-
再生医療等製品
これらの品目をECサイトで販売するには、販売する品目や形態に応じて、薬局開設許可、医薬品販売業許可(店舗販売業、配置販売業、特定販売業)、高度管理医療機器等販売業・貸与業許可など、様々な許可や届出が必要になります。
|
販売品目 |
必要な許可・届出例 |
|---|---|
|
医薬品 |
薬局開設許可、医薬品販売業許可(特定販売業など) |
|
高度管理医療機器 |
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可 |
|
医療機器(一般) |
医療機器販売業・貸与業届出(品目による) |
|
化粧品、医薬部外品 |
許可や届出が不要な場合が多いが、製造販売元などの確認は必要 |
許可なく販売を行った場合、法律違反となり罰則の対象となります。ECサイトでの販売を検討する際は、取り扱う製品が薬機法の対象となるか、どのような許可や届出が必要かを事前に管轄の保健所などに確認することが非常に重要です。
化粧品
ECサイトで化粧品を販売する場合、医薬品医療機器等法(薬機法)による規制を受けます。
仕入れてそのまま販売する場合
製造に関与せず、メーカーから仕入れた化粧品をそのまま販売するだけであれば、原則として特別な許可や届出は必要ありません。
製造・小分け・表示変更などを行う場合
ご自身で化粧品を製造したり、バルクで仕入れたものを小分けしたり、成分表示などを変更して販売したりする場合は、薬機法に基づく許可が必要です。
-
化粧品製造業許可: 化粧品の製造(小分け、包装、表示、保管等を含む)を行う場合に必要です。
-
化粧品製造販売業許可: 製造した化粧品を市場に出荷するために必要です。
薬用化粧品(医薬部外品)を取り扱う場合も、同様に製造販売業許可が必要となります。
許可の申請は、都道府県の薬務課などに行います。
注意点
化粧品の広告・表示についても、薬機法や景品表示法による規制があります。虚偽・誇大な広告は禁止されており、効能効果の範囲などにも注意が必要です。
薬機法に基づく届出・許可
ECサイトで化粧品を販売する場合、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づき規制を受けます。
化粧品には「化粧品」と「薬用化粧品(医薬部外品)」があり、それぞれ扱いが異なります。
-
製造販売業者として販売する場合:
-
自社で化粧品を製造・販売する場合、薬機法に基づく許可が必要です。
-
-
製造に関わらず販売する場合:
-
製造業者から完成品を仕入れて、内容に変更を加えずそのまま販売する場合は、原則として特別な許可や届出は不要です。
-
ただし、輸入品の場合は別途規制がある場合があります。安全な商品を提供するためにも、関連法規を遵守した適切な販売を行いましょう。
健康食品・サプリメント
健康食品やサプリメントのECサイトでの販売についてご説明します。
健康食品の販売自体に特別な許可や資格は基本的に必要ありません。しかし、医薬品と誤解されるような表示や、虚偽・誇大な広告は法律で厳しく規制されています。特に以下の法律に注意が必要です。
-
医薬品医療機器等法(薬機法): 医薬品的な効果・効能を標ぼうする表示は禁止されています。
-
健康増進法: 虚偽・誇大な表示は禁止されています。
-
景品表示法: 実際よりも優良である、有利であると誤認させる表示(優良誤認表示、有利誤認表示)は禁止されています。
また、「特定保健用食品(トクホ)」や「機能性表示食品」といった保健機能食品を販売する場合は、消費者庁の許可や届出に基づいた正しい表示が求められます。
|
食品の種類 |
許可・資格 |
表示規制の例 |
|---|---|---|
|
一般的な健康食品 |
基本不要 |
薬機法、健康増進法、景品表示法など |
|
特定保健用食品(トクホ) |
不要 |
消費者庁長官の許可に基づいた表示 |
|
機能性表示食品 |
不要 |
消費者庁への届出に基づいた科学的根拠の表示 |
消費者に誤解を与えないよう、適切な情報提供と表現に十分注意して販売することが重要です。
薬機法、健康増進法などに基づく表示規制
健康食品やサプリメントをECサイトで販売する際には、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)や健康増進法といった法律に基づく表示規制に注意が必要です。
特に重要なのは、医薬品と誤認させるような表示をしないことです。具体的には、以下のような表現は禁止されています。
-
病気の治療や予防に効果があるかのような表現
-
身体の特定の機能に効果があるかのような表現(「〇〇が改善する」「△△に効く」など)
また、健康増進法では、食品として販売されるものについて、虚偽・誇大その他の消費者に誤認させるような表示が禁止されています。
販売する商品の特性を正しく伝えつつも、法律に抵触しない表現を心がけることが重要です。具体的な表示については、以下の点を参考にしてください。
-
食品表示法に基づく表示: 名称、アレルゲン、保存方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分、原産地など
-
健康増進法に基づく表示: 虚偽・誇大表示の禁止
迷った場合は、消費者庁などの公的機関や専門家へ確認することをおすすめします。
ペット・動物
ペットや動物をオンラインで販売する場合、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に基づき、都道府県知事または政令市の長への「動物取扱業」の届出が必要です。
動物取扱業には以下の種別があり、販売を行う場合は「販売」の届出が必要になります。
-
販売
-
保管
-
貸出し
-
訓練
-
展示
-
競りあっせん
-
譲受飼養
届出を行うには、事業所ごとに動物取扱責任者を選任する必要があります。動物取扱責任者は、動物に関する一定の実務経験や知識・技術を持つ者でなければなりません。
また、動物の健康や安全に配慮した飼養施設の基準を満たす必要があります。
法律の内容は改正されることもありますので、最新の情報は各自治体や環境省のウェブサイトで確認するようにしてください。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく届出
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類。実験動物・産業動物を除く)をECサイトで販売する場合、多くの場合「第一種動物取扱業」の「販売」にあたります。この事業を営むには、事業所ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録が必要です。
「販売」に該当する業種と内容は以下の通りです。
|
業種 |
業の内容 |
該当する業者の例 |
|---|---|---|
|
販売 |
動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
登録申請手続きや必要書類は各自治体によって異なる場合がありますので、管轄の都道府県や政令市の動物愛護管理担当部局にお問い合わせください。
また、動物を販売する際には、購入者に対して事業所において現物確認と対面での説明(電磁的記録を含む文書を使用)が義務付けられています。インターネット上のみで売買契約を成立させることは原則禁止されています。
さらに、動物の飼養施設や管理方法についても細かい基準が定められており、帳簿の作成・保存や定期報告の義務もあります。これらの基準を守らない場合、罰則の対象となることがあります。
輸入品
輸入品をECサイトで販売する場合、様々な日本の法律が適用されます。特に注意が必要なのは以下の点です。
-
関税法: 商品の種類や価格に応じて関税がかかる場合があります。個人輸入の範囲を超える商業目的の輸入には、通関手続きが必要です。
-
食品衛生法: 食品や食器、調理器具などを輸入・販売する場合に適用されます。検疫や検査が必要なケースがあり、場合によっては厚生労働省への届出や許可が必要です。
-
薬機法: 医薬品、医療機器、化粧品などを輸入・販売する場合に適用されます。個人輸入は一定の制限がありますが、販売目的の輸入には厚生労働大臣の許可や届出が必要です。
-
電波法: 無線通信機能を持つ製品(Wi-Fiルーター、Bluetoothイヤホンなど)を輸入・販売する場合に適用されます。技術基準適合証明(技適マーク)がない製品は原則として販売できません。
-
電気用品安全法(PSE法): 電気製品を輸入・販売する場合に適用されます。安全基準を満たしている証明(PSEマーク)が必要です。
これらの他にも、植物防疫法、家畜伝染病予防法など、輸入する品目によって様々な法律の規制を受けます。必要な手続きや規制は品目によって大きく異なるため、事前に経済産業省や関係省庁のウェブサイト、専門家への相談を通じて確認することが重要です。
関税法、食品衛生法など各種法令に基づく規制
輸入品をECサイトで販売する場合、様々な法律に基づいた規制があります。
例えば、食品を輸入して販売するには、食品衛生法に基づく手続きが必要です。また、特定の医薬品や医療機器、化粧品なども、薬機法に基づく許可や届出が必要になる場合があります。
その他にも、輸入品の種類によっては、関税法や植物防疫法、家畜伝染病予防法など、様々な法律で規制されているため注意が必要です。
必要な手続きは輸入する品目によって大きく異なるため、事前に管轄の省庁や専門家への確認をおすすめします。
主な輸入品と関連法規(例)
|
品目 |
関連法規(例) |
|---|---|
|
食品 |
食品衛生法、関税法 |
|
医薬品・医療機器 |
薬機法、関税法 |
|
化粧品 |
薬機法、関税法 |
|
植物 |
植物防疫法、関税法 |
|
動物・畜産物 |
家畜伝染病予防法、動物検疫法、食品衛生法、関税法 |
許可・資格取得以外に必要な手続き・準備
ECサイト開業にあたっては、販売する商品に応じた許可や資格の取得が必要となる場合がありますが、それ以外にも進めるべき手続きや準備があります。
まず、個人事業主として開業する場合は、税務署に「開業届」を提出する必要があります。これは、事業を開始したことを税務署に知らせるためのもので、税務上のメリット(青色申告など)を受けるためにも重要です。
また、ECサイトを構築するための準備も必要です。自社でシステムを開発する方法もありますが、一般的には以下のようなネットショップ作成サービスを利用するのが便利です。
-
Shopify
-
BASE
-
STORES
-
makeshop
これらのサービスは、サイトデザインや決済機能、在庫管理など、ECサイト運営に必要な機能を提供しています。サービスによって特徴や料金が異なるため、ご自身の事業規模や販売計画に合ったものを選びましょう。
税務署への開業届
ECサイトを開業する際、税務署への開業届の提出は必須ではありませんが、提出することでいくつかのメリットがあります。
開業届を出すメリット
-
青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
-
屋号名義の銀行口座が開設できる
-
小規模企業共済に加入できる
開業届は、事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出するのが一般的です。提出方法は、税務署の窓口に持参するか、郵送、またはe-Taxを利用する方法があります。
開業届の提出に必要なもの(一例)
-
個人事業の開業・廃業等届出書
-
マイナンバーカードなど本人確認書類
なお、開業届を提出しなくても罰則はありませんが、上記のメリットを享受するためにも提出を検討することをおすすめします。
ネットショップ作成サービスの選定
ECサイトを開設するには、さまざまなサービスを利用できます。大きく分けて、ASPカート、ECパッケージ、フルスクラッチなどがありますが、初心者の方にはASPカートがおすすめです。
ASPカートは、月額費用や初期費用を抑えて手軽に始められる点が魅力です。代表的なサービスには、以下のようなものがあります。
-
Shopify
-
BASE
-
STORES
-
MakeShop
各サービスによって、機能や料金、デザインの自由度などが異なります。ご自身の販売したい商品や事業規模に合わせて、最適なサービスを選びましょう。
例えば、手軽さを重視するならBASEやSTORES、機能性を重視するならShopifyやMakeShopが候補になります。
サービスの選定にあたっては、以下の点を考慮すると良いでしょう。
-
月額費用・初期費用
-
デザインのカスタマイズ性
-
決済方法の種類
-
集客・販促機能
-
サポート体制
複数のサービスを比較検討し、無料トライアルなどを活用して使い勝手を確認することをおすすめします。
ECサイト運営における注意点
ECサイトを運営する上で、許可や資格の取得だけでなく、法律に基づいた適切な運用が重要です。特に、顧客とのトラブルを避けるために、返品・交換に関する規定と個人情報の取り扱いには十分注意が必要です。
返品・交換に関する規定
特定商取引法に基づき、ネットショップでは返品に関する事項を表示する義務があります。
-
返品の可否とその条件
-
返品の期間
-
返品にかかる送料の負担者
これらの情報を明確に記載し、顧客がいつでも確認できるようにしておくことが大切です。
個人情報の取り扱い
顧客から取得した個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)は、プライバシーポリシーを定めて適切に管理する必要があります。
-
個人情報の利用目的を明示する
-
同意なく目的外に利用しない
-
安全管理措置を講じる
-
第三者提供の制限
これらの対応を怠ると、顧客からの信頼を失うだけでなく、法的な問題に発展する可能性もあります。
返品・交換に関する規定
ECサイト運営において、返品・交換に関するルールは非常に重要です。特定商取引法では、ECサイトのような通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されません。
そのため、返品の可否や条件は基本的に運営側が自由に設定できますが、これらの条件をサイト上や広告に明記しない場合、「法定返品権」により商品受け取りから8日間は返品が認められることがあります。
また、商品の欠陥や契約不履行による返品は、一般的に認められています。トラブルを防ぐため、返品時の送料負担についても明確に記載しておくことが望ましいです。
送料についても、自由に設定できますが、金額を明記する必要があります。「実費負担」のような曖昧な表現は認められません。地域別送料、全国一律送料、一定額以上購入で送料無料など、商品の特性や運営方針に合わせて設定し、分かりやすく表示しましょう。送料を商品価格に上乗せして「送料無料」に見せかける行為は、景品表示法で禁止されていますので注意が必要です。
個人情報の取り扱い
ECサイト運営では、お客様から氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を取得します。これらの個人情報の適切な管理は非常に重要です。
個人情報を取り扱う際には、以下の点に注意が必要です。
-
利用目的の明確化: どのような目的で個人情報を利用するのかを明確にし、お客様に通知または公表する必要があります。
-
同意の取得: 原則として、個人情報を取得する際にはお客様の同意を得る必要があります。
-
安全管理措置: 個人情報の漏洩、滅失、毀損を防ぐため、技術的・組織的な安全管理措置を講じる必要があります。
-
第三者提供の制限: お客様の同意なく、個人情報を第三者に提供することは原則として禁止されています。
-
開示・訂正・利用停止への対応: お客様から自身の個人情報について開示、訂正、利用停止の請求があった場合、適切に対応する必要があります。
これらの個人情報の取り扱いは、主に個人情報保護法によって定められています。ECサイトのプライバシーポリシーなどで、個人情報の取り扱い方針を明確に表示し、お客様が安心して利用できるように配慮することが求められます。
特定企業・サービスに関する補足情報
特定企業やサービスを利用してECサイトを開設する場合、サービスごとの規約や機能によって必要な手続きや準備が異なります。
例えば、STORESやメルカリShopsのようなサービスを利用する場合でも、販売する商品によっては別途、法律に基づいた許可や届出が必要になることがあります。特に中古品を扱う場合は「古物商許可」が必要となるケースが多いです。
ECプラットフォームの選定について触れられており、自社ECとモールECそれぞれの特徴が解説されています。STORESは自社EC、メルカリShopsはモールECに分類されます。
|
サービス |
分類 |
特徴 |
|---|---|---|
|
STORES |
自社EC |
独自性が出しやすい、カスタマイズ性がある |
|
メルカリShops |
モールEC |
集客力がある、規約に従う必要がある |
どちらのサービスを選ぶかに関わらず、販売する商品に応じた許可や届出が必要かどうかは必ず事前に確認しましょう。また、各サービスの利用規約をよく読み、適切な運営を心がけることが重要です。
STORESでのショップ開設と古物商許可
ネットショップ作成サービス「STORES」を利用して中古品を販売する場合、古物商許可が必要になるケースがあります。
STORESでショップ開設した場合でも、古物商許可が必要な場合と不要な場合があります。
|
必要となるケース |
不要となるケース |
|---|---|
|
ネットショップで中古品や古本、古着などを販売する場合(副業含む) |
自宅の不要品を販売する場合 |
STORESで中古品販売を行う際は、ご自身の状況がどちらに当てはまるかを確認し、必要であれば事前に古物商許可を取得しましょう。
メルカリShopsの利用に関する情報
メルカリShopsで中古品を販売する場合、古物商許可の取得が必須となります。フリマアプリのメルカリとは異なり、開設申込時に許認可証の画像を提出する必要があります。
古物商許可を取得せずに中古品販売を行うと、利用制限などの措置が取られる可能性がありますのでご注意ください。
メルカリShopsは、フリマアプリ「メルカリ」の利用者が顧客候補となるため、中古品は人気のジャンルです。法人や個人事業主の方が中古品販売を検討されている場合におすすめのサービスと言えます。
メルカリShopsは、法人利用に便利な以下の機能も備えています。
-
注文・売上管理用のCSVデータダウンロード
-
商品の一括登録機能
-
各種SNS連携機能
-
リユース業界向けEC一元管理システムとのAPI連携
これらの機能を活用することで、効率的に中古品販売事業を展開することができます。
まとめ:スムーズなECサイト開業のために
ECサイトのスムーズな開業には、事前の準備が不可欠です。特に、販売する商品に応じた必要な許可や資格を確認し、適切に申請することが重要です。例えば、中古品を扱う場合は古物商許可、食品を扱う場合は食品衛生法に基づく許可などが必要となります。
また、個人で開業する場合は、税務署への開業届の提出も忘れてはいけません。
ECサイトの運営においては、特定商取引法に基づいた表示や、返品・交換に関する規定、個人情報の取り扱いなど、法律を遵守した対応が求められます。これらの手続きや準備を丁寧に行うことで、安心して事業を進めることができます。